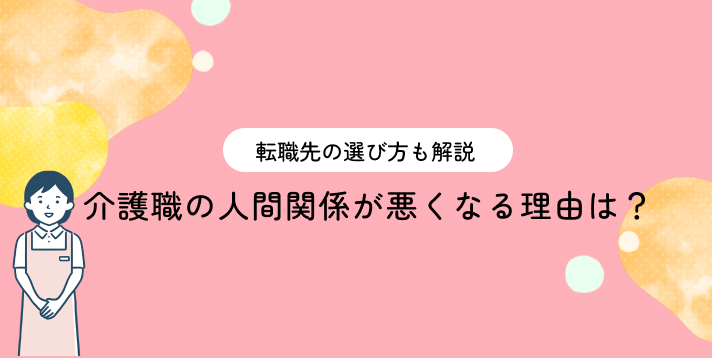「職場の人間関係の悪さから転職を検討しているが、転職先の人間関係にも不安がある」
「人間関係が良好な職場に転職したいが、見極め方がわからない」
介護現場の人間関係に悩んでいる方のなかには、上記のような悩みがある方もいます。
そこで本記事では、介護職の人間関係が悪くなる理由や人間関係が良好な現場を見分けるポイントなどを解説します。人間関係を重視する方向けにおすすめの転職先も紹介しているため、ぜひご覧ください。
介護職の人間関係が悪くなる理由

介護職として働く方のなかには、職場の人間関係に悩んでいる方も少なくありません。介護職の人間関係が悪くなる理由として挙げられるのは、以下3つの理由です。
- 多様な価値観の職員が働いているから
- 人手不足が慢性化しているから
- 教育体制が整っていないから
多様な価値観の職員が働いているから
介護の現場で働く職員の年齢層は、10代後半の若年層から65歳以上のシニア層まで幅広いです。また、介護業界以外から未経験で転職してきた職員も多く働いています。
実際に、公益財団法人介護労働安定センターが実施した「令和5年度介護労働実態調査」によると、介護労働者がこれまで勤務した職場での仕事内容は「介護・福祉・医療関係以外の仕事」が61.7%でもっとも多く、介護職として働く方のバックグラウンドは多岐にわたります。
さまざまな価値観や職業観をもつ職員が共に働くため、意見が衝突しやすく、職員間の人間関係が悪くなる原因となります。
くわえて、介護職は単純な年功序列ではなく、経験年数や資格の有無、スキル・知識の到達度を客観的に評価する制度などで、職員を評価する職場も少なくありません。評価基準がわかりやすく周知されない場合「なぜあの人が評価されるのか」といった不満につながる可能性もあります。
参照:公益財団法人介護労働安定センター「令和5年度介護労働実態調査 介護労働者の就業実態と就業意識調査 結果報告書」
人手不足が慢性化しているから
厚生労働省が2024年に試算した結果によると、2026年には介護職員が25万人不足する見込みです。思うように人材確保が進まない職場では人手不足が慢性化しており、職員間の人間関係が悪くなる原因となっています。
介護現場ではチームで仕事を進める職場が多いため、人手が足りなければ職員1人あたりの業務量が増えてしまいます。たとえば、利用者様の居室のシーツ交換を18床行う必要がある場合、3人であれば1人あたり6床で済むものの、2人であれば9床交換する必要があります。
このように1人あたりの業務量が増えてしまうと、相手を思いやる余裕がなくなってしまう可能性があります。結果的に、職員間のトラブルを招くケースもあるでしょう。
参照:厚生労働省「第9期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について」
教育体制が整っていないから
人手不足が深刻な職場では、介護未経験の新人が入職しても、十分に教育できないケースがあります。教育体制が整っていないことが原因で、人間関係が悪くなる場合もあります。
たとえば、先輩職員から指導を受けていないにも関わらずミスをして攻められれば、新人職員は周囲に不信感を抱いてしまうでしょう。特に介護現場では、ひとつのミスが利用者様の安全を脅かしかねません。
必要な知識・技術を学ぶ機会がなく安心して働けない職場ではストレスがたまり、人間関係が悪化する原因になります。
介護職が「人間関係の悪い職場から転職したい」と思ったらやるべきこと

介護職が「人間関係が悪いことが理由で転職したい」と思ったら、転職前に以下を実践してみましょう。
- 人間関係を改善するための対処法を実践する
- 上司・相談窓口へ相談する
- 改善しなければ転職を検討する
1.人間関係を改善するための対処法を実践する
介護職が働く職場は、基本的にどの職場でも人と関わります。そのため、人間関係が理由で転職したとしても、転職先に問題がないとは限りません。人間関係以外に「転職したい」と感じるポイントがない場合、以下を意識して人間関係を改善できるよう努めてみましょう。
- 笑顔で相手に接する
- 意見が対立しても相手の考えを否定しない
- 悪口に参加しない
- 適度な距離感を保つ
人間関係に関する問題は、介護業界に限らず多くの職場で存在します。転職を決断する前に、自分でできることを試してみましょう。
2.上司・相談窓口へ相談する
ステップ1を実践しても人間関係を改善できなかった場合、現状を整理したうえで信頼できる上司に相談しましょう。シフトの調整や配置転換など、現場でできる対応を提案してもらえる可能性があります。
また、悩んでいる内容がハラスメントに該当する可能性が高い場合、社内・法人内に相談窓口が設置されているため、相談してみるのも一つの方法です。社内の人間に相談することに不安がある場合、以下のような外部の相談窓口を利用する方法もあります。
| 相談機関名 | 概要 |
| 総合労働相談コーナー (各都道府県労働局) | 職場のトラブルに関する相談や、解決のための情報提供をワンストップで実施 |
| 法テラス (日本司法支援センター) | 問い合せ内容に応じて解決に役立つ法制度や関係機関の相談窓口を案内 |
| みんなの人権110番 (全国共通人権相談ダイヤル) | ハラスメントや差別など、さまざまな人権問題についての相談を受付 |
悩みの内容や希望に応じて、相談先を決めましょう。
3.改善しなければ転職を検討する
上司や相談窓口などに相談しても悩みが解決できなかった場合、新たな職場への転職を検討しましょう。転職の選択肢はおもに以下の2つです。
- 介護業界内の別の職場に転職する
- 異業種の職場に転職する
介護職の仕事そのものが好きであれば、介護業界内の別の職場に転職するのがおすすめです。ただし、介護サービスごとに仕事内容が異なります。違いを理解したうえで転職先を選びましょう。
以下の記事では、介護職が働く高齢者施設の種類を解説しています。各施設の概要や入居対象者なども紹介しているため、転職先選びにお役立てください。
高齢者施設にはどんな種類があるの?特徴から選び方まで解説します!
人間関係が良好な介護現場を見分けるポイント

人間関係が良好な可能性が高い介護現場を見分けるポイントは、以下の4つです。
- スタッフの年齢層・男女比に偏りがない
- 人員配置に余裕がある
- 頻繁に求人を出していない
- 給与が高すぎない
スタッフの年齢層・男女比に偏りがない
働くスタッフの年齢層・男女比が適度に分散されているかを確認しましょう。たとえば若年層のスタッフが少なくベテランが多い場合、スタッフの育成体制が確立されておらず、入職してから苦労する可能性があります。
また、女性スタッフに比べて男性スタッフが少ない場合、男性利用者様の同性介助や「体格のよい男性利用者の身体介助」といった体力的に負荷のかかる業務が、数少ない男性に集中してしまう可能性もあります。
スタッフの年齢層・男女比に偏りがなく、個々が働きやすい環境を整えている職場を見つけましょう。
人員配置に余裕がある
先述したとおり、人手不足が慢性化している職場では1人あたりの業務量が多くなりがちです。しかし、人員配置に余裕がある職場であれば、スタッフや利用者様とのコミュニケーションを十分に取れるため、人間関係も良好な可能性が高いです。
人員が十分に確保できていれば、急な欠勤や体調不良、トラブル対応などのイレギュラーにも対応できます。そのため、人手不足が原因の残業や休日出勤による、ストレス・不満などの蓄積も抑制できます。
頻繁に求人を出していない
転職サイトに頻繁に求人を出していない職場は、人間関係が良好で働きやすい可能性が高いです。一方で、頻繁に求人を出している職場は、なんらかの理由で離職率が高い可能性があります。必ずしも人間関係が原因とは限らないものの、人手不足が慢性化している恐れがあるため、注意が必要です。
給与が高すぎない
周辺の求人と比べて、給与が高すぎないかどうかもポイントです。給与が高い職場は一見魅力的に見えるものの、人間関係が悪くスタッフの定着率が悪い職場であることから、好条件を提示せざるを得ない可能性があります。
また、給与は高いものの、実際は「休憩時間が確保できないほどの業務量がある」「ぎりぎりの人数でシフトを回しているため法定休日や有給休暇が取得できない」といった職場もあります。そのため、地域の相場より給与が高い職場に転職したい場合は、その理由を確認して納得したうえで転職しましょう。
【人間関係重視】介護職の転職先の選び方

ここからは、職場の人間関係を重視する方向けに、以下の希望別におすすめの転職先を紹介します。
- 職員数が少ない施設で働きたい
- 基本的に1人で仕事を進めたい
- アットホームな雰囲気で働きたい
職員数が少ない施設で働きたい
働く職員数が少ない施設で働きたい場合「グループホーム」への転職がおすすめです。1ユニットあたりの入居者数は5人~9人であり、職員もフロアごとに固定されているのが一般的です。現場で関わる人の数は比較的少なく、コミュニケーションも取りやすいでしょう。
加えて、グループホームの入居条件には「医師により認知症と診断されていること」が含まれています。そのため、認知症ケアを学べるのも魅力です。
また、特別養護老人ホームでも「ユニット型」の施設であれば、配置される職員の数も少ない傾向があります。ただし、同じ特別養護老人ホームであっても「従来型」の場合は、1フロアに配置される職員の数が多いため、特別養護老人ホームへの転職時は種類を確認しましょう。
基本的に1人で仕事を進めたい
介護職としての経験年数がある程度あり、基本的に1人で仕事を進めたい場合は「訪問介護事業所」への転職がおすすめです。基本的に1人で利用者様宅へ訪問するため、同僚と必要以上にコミュニケーションを取ることがなく、人間関係に悩まされにくいのが魅力です。
ただし、自分1人で判断する場面もあり、フォロー体制は事業所によって異なります。そのため、緊急時の対応に不安がある場合は、面接時にフォロー体制について確認したうえで、転職先を決めましょう。
以下の記事では、訪問介護事業所で働く「訪問介護員(ホームヘルパー)」の仕事内容や働き方などを解説しています。訪問介護への転職を検討中の方は、ぜひあわせてご覧ください。
訪問介護員への転職は大変?働き方や1日のスケジュール例もご紹介
アットホームな雰囲気で働きたい
アットホームな雰囲気の職場で働きたい場合「デイサービス」への転職がおすすめです。日勤中心で、職員や利用者との距離が近く、アットホームな雰囲気の職場が多いです。
また、夜勤がない職場が多く、勤務時間もほぼ同じため「夜勤に入れない」「早番しか入れない」など、個人の希望によるシフト上のトラブルが起きにくいでしょう。
ただし、夜勤手当は支給されないため、ほかの職場と比べると給与は低い傾向があります。待遇面を重視する方は給与額を確認し、納得して働き続けられるかどうかを検討したうえで転職しましょう。
介護職の転職でよくある質問

介護職の転職でよくある質問は以下の3つです。
- 質問1.介護職が新人に厳しい理由はなんですか?
- 質問2.人間関係で悩む介護職は少ないですか?
- 質問3.特定の職場の離職率を調べる方法はありますか?
質問1.介護職が新人に厳しい理由はなんですか?
人手不足の職場では、先輩職員も自身の業務で手一杯になっている傾向があります。コミュニケーションが十分に取れない職場では、新人が職場になじめず「新人に対して厳しい」と感じるケースがあります。
質問2.人間関係で悩む介護職は少ないですか?
介護現場で人間関係に悩む職員は多いです。2020年にTSグループが実施した調査によると、介護職を離職した方が挙げている理由として「職場の人間関係に苦労したから」が46.6%と、多くの割合を占めています。また、約7割が介護の仕事は好きだが離職している実態もあり、仕事内容とは別の部分で悩んでいる職員も多いといえます。
介護現場で悩まされる人間関係のあるあるとして、以下のような事例があります。
- 勤務歴が長い職員が多い職場に入職したがなじめない
- おむつ交換や入浴介助などの大変な業務を避けるベテラン職員がいる
- 職員全員が自分の業務に手一杯でまともにコミュニケーションが取れない
- 高圧的な言い方をするベテランがいて新人が萎縮してしまう
上記のような事例が原因となり、離職につながるケースは少なくありません。
参照:株式会社トライト「介護職の離職に関する実態調査2020」
質問3.特定の職場の離職率を調べる方法はありますか?
人間関係が良好な職場の判断材料として、各職場の離職率を調べたうえで転職先を決める方法もあります。特定の職場の離職率を調べる方法は、以下のとおりです。
- 「介護サービス情報公表システム」で退職者数を確認する
- 「退職者数÷在籍者数×100」の計算式で離職率を計算する
- 介護業界の離職率平均と比べて離職率が高い職場かどうか判断する
以下の記事では、上記の離職率の調べ方を画像付きで解説しています。転職で後悔する原因も紹介しているため、転職に失敗したくない方はぜひあわせてご覧ください。
介護転職で後悔する原因は?成功させる5つのコツ・希望別の転職先の選び方も解説
まとめ

介護職は、転職先に困らないほど多くの求人があります。しかし、転職先の人間関係が必ずしも良好であるとは限らないため、安易に転職してしまうと後悔する可能性があります。
本記事で紹介した、人間関係が良好な現場を見分けるポイントや転職先の選び方などを参考に、自分が納得して働き続けられる職場を見つけましょう。
養護・特別養護老人ホーム 白寿荘を運営する社会福祉法人 「神奈川県 匡済会」では、養護・特別養護老人ホームや地域ケアプラザなどで一緒に働くスタッフを募集しております。
求人情報にご興味をお持ちいただいた方は、ぜひ以下よりご覧ください。