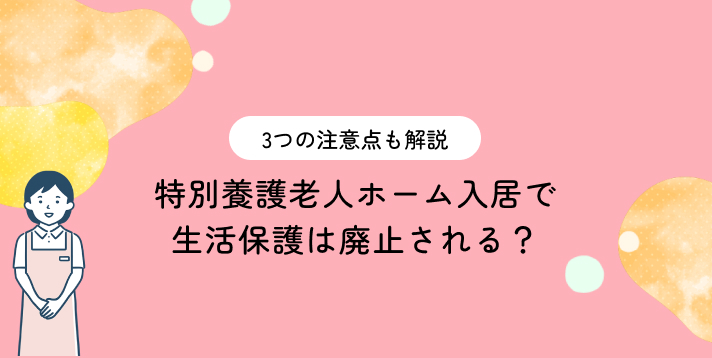「特別養護老人ホームへの入居にあたって、生活保護の給付が廃止されるか不安がある」
「生活保護受給者が特別養護老人ホームに入居する場合の注意点が知りたい」
生活保護を受給されている方のなかには、上記のような悩みがある方もいるのではないでしょうか。
特別養護老人ホームへの入居後も生活保護は廃止されず、介護扶助費や生活扶助費が支給されます。ただし、利用料の本人負担が発生するケースもあるため、注意点を理解したうえで入居を検討する必要があります。
そこで今回は、特別養護老人ホームでかかる費用と生活保護費で賄われる範囲を中心に解説します。入居するにあたって費用に関する不安が解消できる内容のため、ぜひ最後までご覧ください。
特別養護老人ホーム入居後も生活保護は原則廃止されない

特別養護老人ホームに入居した場合、生活保護は原則として廃止されません。おもに「介護扶助費」や「生活扶助費」が支給されるため、生活保護を受給していたとしても安心して生活できます。
特別養護老人ホーム利用でかかる費用は、大きく分けて以下の3つです。
- 介護サービス費(おむつ代含む)
- 食費
- 日常生活費
上記費用に対応して支給される扶助を解説します。
介護扶助費で賄われる範囲
介護扶助費で賄われるのは「介護サービス費(おむつ代含む)」と「食費」です。介護扶助で賄われる費用は、施設側に直接支払われます。
介護サービス費は、施設の設備や職員体制、施設が提供するサービスなどに対してかかる費用です。また食費には、食事の材料費や調理費などが含まれています。
介護扶助の対象者は、生活保護受給者のうち要介護(要支援)認定を受けている方が対象です。介護保険制度と介護扶助の割合は、以下の表のとおりです。
| 区分 | 対象者 | 費用負担の割合 | |
| 介護保険第1号保険者 | 市区町村の区域内に住所がある65歳以上の方 | 介護保険給付9割 | 介護扶助1割 |
| 介護保険第2号保険者 | 以下3つを満たす方 ・市区町村の区域内に住所がある ・40歳以上65歳未満の医療保険(社会保険)加入者 ・特定疾患により介護が必要な状態 | 介護保険給付9割 | 介護扶助1割 |
| 被保険者以外の方 | 以下3つを満たす方・市区町村の区域内に住所がある・40歳以上65歳未満の医療保険(社会保険)未加入者・特定疾患により介護が必要な状態 | 介護扶助10割 | |
参考:横浜市健康福祉局生活支援課「指定介護機関のしおり」
生活保護を受けている40歳以上65歳未満であって医療保険未加入の方は、国が定める特定疾患が原因で介護に必要になった場合のみ生活保護制度で介護サービスが利用可能です。
生活扶助費で賄われる範囲
生活扶助費で賄われるのは「日常生活費」と「保険料」です。
日常生活費は、日常生活を送るのに必要な費用に対してかかります。たとえば、理美容代や被服費、レクリエーションにかかる費用などが該当します。また先述のとおり、介護サービスを受けるのに必要な介護保険料も含まれます。
生活保護を受給しながら特別養護老人ホームに入居する場合の注意点

生活保護を受給しながら特別養護老人ホームに入居する場合、以下の3点に注意しましょう。
- 基準費用額を超える居住費・食費は提供されない
- 本人負担が発生する可能性がある
- 基本的には多床室への入居となる
基準費用額を超える居住費・食費は提供されない
生活保護を受給している方が特別養護老人ホームに入居する場合、居住費(滞在費)と食費については、基準費用額を超える金額の提供を受けることはできません。
特別養護老人ホームの居住費と食費の基準費用額は以下の通りです。
| 費用項目 | 基準費用額(日額(月額)) | |
| 食費 | 1,445円(4.4万円) | |
| 居住費 | 多床室 | 885円(2.6万円) |
| 従来型個室 | 1,171円(3.6万円) | |
| ユニット型個室的多床室 | 1,668円(5.1万円) | |
| ユニット型個室 | 2,006円(6.1万円) |
出典:厚生労働省 労働局「介護報酬改定率、多床室の室料負担、基準費用額(居住費)
たとえば、多床室に入居した場合、居住費の基準費用額は日額885円(月額2.6万円)となります。また、基準費用額を超える分を利用者に自己負担させることも認められていません。よって生活保護受給者の方は、基準費用額の範囲内でサービスを受けることになります。
本人負担が発生する可能性がある
生活保護受給者の方に一定程度の収入がある場合、介護費用の一部負担が必要になるケースがあります。具体的には、収入が生活費を超える場合は本人負担が発生する可能性があります。一方で、収入額が生活費よりも少ない場合は、本人負担は発生しません。
また、本人負担額が発生する場合であっても、上限額は最大24,300円と定められています。具体的には、15,000 円+食費(300 円 / 日 × 実日数)であり、例外的に認めている場合は居住費も含まれます。
基本的には多床室への入居となる
生活保護受給者の方が特別養護老人ホームへ入居する場合、基本的には2~4人程度で1つの部屋を使用する「多床室」への入居になることを認識しておきましょう。
個室が利用できる施設も
原則は多床室の利用になるものの、2011年から実施されている「社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業」に協力している特別養護老人ホームであれば、ユニット型個室が利用できる可能があります。
この制度は、低所得者の方の介護サービスにかかる負担額を軽減することを目的とした制度であり、従来型の多床室と比べて居住費が高いユニット型個室にも入居可能となります。
ただし、全ての特別養護老人ホームで軽減が受けられるわけでなく、事業に協力する施設のみで適用される点に注意しましょう。
介護施設と生活保護に関してよくある質問3つ

特別養護老人ホームをはじめとした介護施設と生活保護に関して、よくある質問は次の3つです。
- 特養以外にも生活保護を受給しながら利用できる施設はありますか?
- 生活保護受給者を受け入れている施設はどのくらいありますか?
- 生活保護を受けるために世帯分離できますか?
質問1.特養以外にも生活保護を受給しながら利用できる施設はありますか?
特別養護老人ホーム以外で生活保護を受給しながら利用できるのは、以下3つの施設です。
- 有料老人ホーム
- グループホーム
- サービス付き高齢者向け住宅
有料老人ホームは民間の介護施設であるものの、生活保護受給者でも入居できる施設があります。ただし、施設によって受け入れ状況は異なるため、事前に確認が必要です。生活保護の扶助で家賃や生活費をまかなえる範囲の施設を探しましょう。
グループホームは、認知症の方が少人数で共同生活する施設です。入所施設のなかでは比較的低価格で利用できるものの、生活保護受給者の受け入れ可否は施設によって異なります。利用を検討する際は、受け入れ状況と利用料を確認しておくことが大切です。
サービス付き高齢者向け住宅は、バリアフリー設計の賃貸住宅に安否確認や生活相談のサービスが付いた施設です。介護施設のなかでは、初期費用や家賃が比較的安価です。ただし介護が必要な場合は、外部サービスを利用する必要がある点に注意しましょう。
上記の施設は、特別養護老人ホームと比べると生活保護受給者の受け入れ状況にばらつきがあります。施設探しの際は、生活保護受給者の受け入れ実績がある施設を見つけることが重要です。
なお、生活保護受給者の方が利用できる施設に「養護老人ホーム」があります。養護老人ホームは現在置かれている環境では生活が難しく、経済的にも厳しい65歳以上の高齢者が入居できる施設です。ただし社会復帰を目指す施設のため、介護が必要な方が生活する特別養護老人ホームとは役割が異なります。
以下の記事では、特別養護老人ホームと養護老人ホームの違いをさらに詳しく解説しています。それぞれの施設のメリット・デメリットも紹介しているため、養護老人ホームとの違いについて詳しく知りたい方は、ぜひご覧ください。
参考記事:養護老人ホームと特別養護老人ホームの違いとは?それぞれのメリット・デメリットも紹介
質問2.生活保護受給者を受け入れている施設はどのくらいありますか?
平成26年に公益社団法人全国有料老人ホーム協会が実施した調査によると、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅が生活保護受給者を受け入れている割合は、以下のとおりです。
| 介護付き有料老人ホーム | 住宅型有料老人ホーム | サービス付き高齢者向け住宅 |
| 11.3% | 49.0% | 32.1% |
施設のスタッフによって介護が受けられる「介護付き有料老人ホーム」の受け入れ状況は最も低く、外部の介護事業所から介護サービスを受ける「住宅型有料老人ホーム」や「サービス付き高齢者向け住宅」は、生活保護受給者を比較的受け入れていることがわかります。
受け入れ状況や入居条件は施設によって異なるため、民間施設への入居を検討する際は各施設の受け入れ実績の確認が大切です。ケアマネジャーや福祉事務所のケースワーカーに相談し、生活保護受給者の入居実績がある施設を探しましょう。
参考:公益社団法人全国有料老人ホーム協会「有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅に関する実態調査研究事業報告書」
質問3.生活保護を受けるために世帯分離できますか?
同一世帯の家族が生活保護を受給する場合、世帯分離できる可能性があります。厚生労働省は以下のような「状況を鑑みてやむを得ない場合」に、生活保護を受けるにあたって世帯分離できるとしています。
たとえば、父親・母親・息子・息子の妻が同居している場合に、父親に介護が必要になって介護施設に入居するとします。しかし、介護施設の費用を支払うことで「要保護世帯」となる場合「父親」のみを世帯分離し、母・息子・息子の妻と世帯を分けることが可能です。
生活保護を受けるために世帯分離できる条件は「生活保護法による保護の実施要領について」のページで、さらに詳しく確認できます。
まとめ

特別養護老人ホームに入居したとしても生活保護は廃止されず、施設利用でかかる介護サービス費や日常生活費などに介護扶助費・生活扶助費が支給されます。また一定額の収入がある場合でも、自己負担の上限額が決まっているため、安心して利用することが可能です。
本記事で紹介した、生活保護を受給しながら特別養護老人ホームに入居する場合の注意点も参考に、費用面の不安なく利用できる特別養護老人ホームを選びましょう。
白寿荘は、横浜市泉区にある特別養護老人ホームです。介護保険法の精神に基づき、65歳以上または40歳以上65歳未満の特定疾患のある方を対象にサービスを提供しています。
施設介護サービス・ショートステイサービス・デイサービスをご利用いただく皆様に1つのフロアでサービスを提供しているため、人との繋がりが作りやすいのが特徴です。近隣病院と協力体制を築いており、安心して生活していただける環境を整えています。